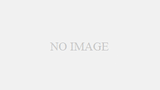90年代に加速したインターネット
一般消費者の間でインターネットの利用が進んだのは90年代です。
丁度その頃、Windows95というOSが普及した時期で、今までは高すぎて一般消費者では手が届かなかったパソコンも、同OSの低価格化によって高嶺の花では無くなりました。
パソコンとOSの低価格化、そして個人宅向けのプロバイダ契約が普及した結果、95年頃より急速に一般家庭へとネットの文化が浸透しました。
95年頃のネット社会は今とは対照的なものです。
一部のユーザーがあくまで純粋に趣味の一環でネットを利用していたに過ぎず、いわゆる機械やパソコンに詳しい理科系の男性や若者が細々とネット上のコミュニティに参加していました。
今のような巨大なコミュニケーションの場はありません。
個人が自作したホームページと掲示板、そしてオンラインチャット等が当時のネット社会では主要なコミュニティでした。
そもそも常時接続の環境ではなく、ネットの利用料金が安価になる夜間に限り利用する人々が殆どだったため、情報がリアルタイムで交換される事はありません。
ホームページの更新頻度もピンキリで、まめな管理人の方は毎日更新しましたが、大多数が一週間に一度あれば高頻度と評価される程の環境です。
昔のネットはあくまでバーチャルな世界だった
掲示板に投稿されるコメントにレスがつくのも、翌日であれば早い方であり、チャットのようなリアルタイムのコミュニティ以外は、今のように双方向性が見られませんでした。
あくまで別の世界という位置づけであり、今現在のようにリアルと地続きの感覚が利用者には無く、バーチャルな世界として扱われていました。
そのため良し悪しは別として当時からネット上では、ユーザー同士の小競り合いや誹謗中傷、掲示板での迷惑行為や物騒な犯行予告などがありましたが、あくまでバーチャル空間での出来事とされ、今日の様に行政や警察、学校等が真剣に対応する事例は稀でした。
迷惑行為は昔からありましたが、いわゆる荒らしや犯行予告も文字通りバーチャルなものであり、リアルとは断絶した異質な空間です。
ところが2000年代になりますと、状況が色々と変わっていきます。
携帯電話の普及とスマートフォンの登場によって、インターネットの大衆化がより加速しました。
それまではITやパソコンにある程度詳しい一部のユーザーが使うものだったネットが、2000年以降は主婦やOLや高齢者、そして子供たちと今まであまりネット社会に参加していなかった属性の方々が急増していきます。
2000年以降ECサイトが爆発的に増加
行政や企業も積極的に参加を行ってきました。
今まではテレビゲームのような架空現実だったネット社会が、その頃には現実の街に近い存在になり、パソコンの低価格化はより一層加速し、スマートフォンの費用対効果もアップした結果、日本国民の半数以上がネットユーザーになる今日に繋がります。
大手企業が新しいビジネススタイルとして、ネット空間に相次いで公式サイトをオープンし、ECサイトが爆発的に増加しました。
今まではテレビやカタログが主流だった通信販売というビジネスが、2000年代になりますと、パソコンやスマートフォンを通して行うものに変化し、人々の暮らしはより一層便利になります。
そして実際の街に近い数々のネットコミュニティが開設していき、SNSやブログや質問サイト等が沢山設けられていきました。
インターネットを通して出会いを求める人々も増えていき、またネットを通して素人でも意見が発信出来る環境が整っていきます。
今までメディアを所有出来るのは大手出版社やテレビ局などの専売特許でしたが、SNSの流行やブログの登場によって、素人でも簡単に自分の思いを世界に向けて投稿したり、日々の写真を不特定多数の人々に見てもらえる環境になりました。
これからはネット動画の時代か?
そして2010年代の今日ですが、今度は大手動画サイトが上陸し、ネット社会の図式が変わり始めています。
動画という情報量が多いコンテンツが一般的な端末でも扱えるようになり、またユーザーが気軽に手元の動画をアップロード出来る仕組みの動画サイトが各地に設けられた結果、様々なコンテンツが自宅に居ながら満喫出来るようになりました。
今まではブログやSNSを通して個人が配信出来るのは短いメッセージとデジカメで撮影した写真程度でしたが、ネット動画サイトの登場によって、長時間の映像を気軽に不特定多数のユーザーに見せられるようになり、面白いペットの動画を撮影した投稿者が人気者になったり、それをテレビ局がバラエティー番組で放送したりと、より一層リアルとネット社会の一体化が進んでいます。
ネットバンクやネット通販サイト、SNSや動画サイトは既に現代人の暮らしに欠かせない存在になっており、日常生活の雑用から行政や企業との契約や手続きも、今ではオンラインでほとんど可能です。
ネットは新しい社会的なインフラとなっており、既存の媒体でしか情報を得ていない人々との情報格差が昨今深刻な問題になりつつあります。