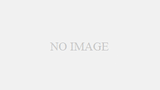1.労働審判とは
労働審判は、日本にある法制度のうち労働審判委員会が審判役となって労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案を斡旋することによって、当該紛争の解決を図る手続のことを指します。
まだこの制度は出来てからそこまで年月は経っておらず、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度です。
正式にこの制度の運用が開始されたのは2006年4月のことです。
制度ができてから、適用された紛争案件の数はかなりの増加傾向にあります。
これは、労働者側がこの制度を利用しやすいというメリットによるものです。
ただ、会社側にとっては労働者側から訴えられやすい制度でもあるといえます。
この制度ができた目的ですが、解雇や給料の不払などといった事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルをその実情に即して迅速・適正・そして実効的に解決することを目的として生まれました。
労働審判委員会は、労働裁判官一人と労務関係の専門的な知識・経験を有していることが認定されている人2名とで構成されています。
この手続の最大の特徴ですが、原則的に3回以内の期日で審理を終結することが法律によって定められています。
ですので、当事者は早期に的確な主張や立証を行うことが重要です。
2.労働審判を利用する際には弁護士に依頼することが望ましい
利用するときには、法律の専門家である弁護士に依頼することが最も望ましいでしょう。
この手続をとるときに弁護士を代理人とした人の割合はデータで全体のうち約71.1%の人が依頼しており、その場合の解決率は約84.1%が解決しています。
データから見えてくることは、弁護士に依頼して紛争案件の解決を進めたほうが労働者・使用者の双方にとって納得しやすいということです。
それでは、どうしてこの手続の場において早期に解決することが求められるのかですがあくまでも、労働審判で対象となるのは労働紛争に限定されており多い事例ではいじめ・ハラスメント・セクハラ・給料未払い・労働条件の引き下げなどといった労務に関連するトラブルのみを対象として審判します。
対象とならない紛争案件もあり、労働組合と労働者との間で起きた紛争については対象外ですので気を付けましょう。
社員同士の紛争に関しても、対象外となります。
裁判になると労働者と使用者側の間の意見が対立して平行線がたどるとしばしば長期化しやすく労働者にとって不利になるデメリットがあるため、こうした場では労働者が利用しやすいように迅速に対応する目的で3回以内で審理するというわけです。
審理を行った結果、双方が合意に達した場合には労働審判は和解と同程度の効力を有します。
3.まず調停を行うことによって話し合いの中で解決を見出す
労働審判の内容ですが、まず調停を行うことによって話し合いの中で解決を見出すことが主体です。
ただ、調停で解決しないという場合でも委員会側は事案の解決に即した対応を出来るだけとり、通常の裁判よりも柔軟に対応するという特徴を持っています。
時間が限られているため、審理の第1回期日が特に重要となります。
その時までに双方がすべての主張や証拠をできるだけ提出しなければなりません。
つまり、1回目の審理で大まかな心証を持つことになることは覚えておきましょう。
答弁書なども用意する必要がありますが、答弁書の内容いかんによっては質問の組み立てや心証などにも大きな影響を与えることになりかねませんので注意します。
そうしたリスクを考えると、会社側・労働者側双方が弁護士を立てて解決を図るのが望ましいです。
一度心証を害してしまった場合においては、挽回するのはかなり困難になりますのでできるだけ丁寧に接するようにします。
4.第2回期日から第3回期日までの間はあまり間隔をおかずに開催される
第2回期日では、一回目の審理の際に整理された争点及び示された調停案をもとに意見を双方が用意したうえで妥協点または合意点を決めていくのが主体です。
第2回期日で大体決まることが多いのですが、決まらなかった場合においては第3回期日のときにもう一度話し合いを行います。
第2回期日から第3回期日までの間はあまり間隔をおかずに開催されることも留意しましょう。
もしも、紛争事案が複雑化した場合やこの審理を行うことが適当でないと委員会側で判断したときにおいてはそこで終了させることができます。
その場合、訴訟へと進展することになり裁判で争って決着を図ります。
労働紛争の解決方法にはこの手続以外にも様々な方法があり、この制度はあくまでも解決方法の一つという意味合いです。
簡易裁判所でできる少額訴訟手続や民事調停手続も紛争の解決方法の一つですので、どの方法が自分に適しているのかに関しては各裁判所の窓口に尋ねておくのも一つの方法です。
窓口には、裁判所における各種手続を分かりやすく説明したリーフレットがあるほかに少額訴訟手続の訴状や調停申立書などの定型用紙も備え付けられています。
それから、それぞれの手続の概要や申立ての方法について説明を受けることも可能ですので分からないことは聞いて解決していくと良いです。